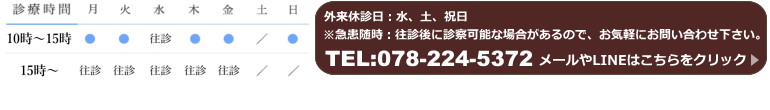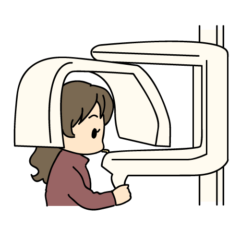神戸市東灘区岡本にある歯医者さん、阪急岡本駅から徒歩2分の岡本歯科ロコクリニックです。待ち時間の少ない、ほぼ無痛(痛くない)虫歯治療、しっかりとした説明、日曜診療などに取り組んでいます。
子どもが食事をする時、親は「よく噛んで食べなさい」と注意することがよくあります。その光景を経験してきた人も多いのではないでしょうか。しかしなんで「よく噛む」ということが大事なのか説明できますでしょうか?今回も引き続き、よく噛むことで消化を助けるといわれるのはなぜなのか、またそれ以外にもあるメリットを詳しくご説明していきます 。
よく噛むことにより得られるメリットはいくつもありますが、唾液の分泌が増えるというメリットもあります。では噛むことで増えた唾液にはいったいどのような役割があるのでしょうか?唾液の様々な役割について取り上げてみましょう。
よく噛むことにより得られるメリットはいくつもありますが、唾液の分泌が増えるというメリットもあります。では噛むことで増えた唾液にはいったいどのような役割があるのでしょうか?唾液の様々な役割について取り上げてみましょう。
人間の唾液は、主に耳下腺、顎下腺、舌下腺の3大唾液腺から分泌され、その量は健康な成人で一日1.0~1.5ℓといわれています。食事の際によく噛むと、これらの唾液腺が刺激され多くの唾液が分泌されるのです。
その唾液の役割は酵素アミラーゼがでんぷんを分解し消化しやすくするだけではありません。
唾液には食べ物のカスや歯垢(プラーク)を洗い流す自浄作用があります。また口中の細菌の増加を抑え、むし歯予防につながります。
粘性のあるムチンが粘膜を保護し、発音が円滑になります。口の中は傷がついても早く治ります。これは唾液に粘膜修復作用があるからです。
その他にも唾液には有害物質を希釈したり、味覚の感覚を助けたりするといった役割があるのです。
噛むことと子どもの脳の発達には何か関係があるのでしょうか?噛むことが脳に及ぼす影響について考えてみましょう。
たくさん噛むと脳が刺激され血流が活発になり、その結果脳も活性化されることは以前からいわれていました。脳の中では前頭前野という部分や海馬を始め様々な部分が活性化されます。このうち前頭前野は情報の統合力、判断力、集中力など、社会生活を営む上で大切な働きをつかさどる領域です。また海馬の活性化は記憶力アップにつながります。
例えば前頭前野の発達が悪ければ、物事を計画し判断して行動することが難しくなります。突然キレる子どもが増えていますが、これは前頭前野の発達が悪いか、機能が低下しているからだと考えられています。
他にも、噛むことにより脳内に緊張を和らげる物質が増えます。これにより気持ちが落ち着き、集中力や記憶力も高まります。
また、よく噛めば顔の筋肉が発達します。その結果、言葉がきれいに発音でき、顔の表情も豊かになります。
以上のように、噛むことと脳の発達には深いつながりがあるのです